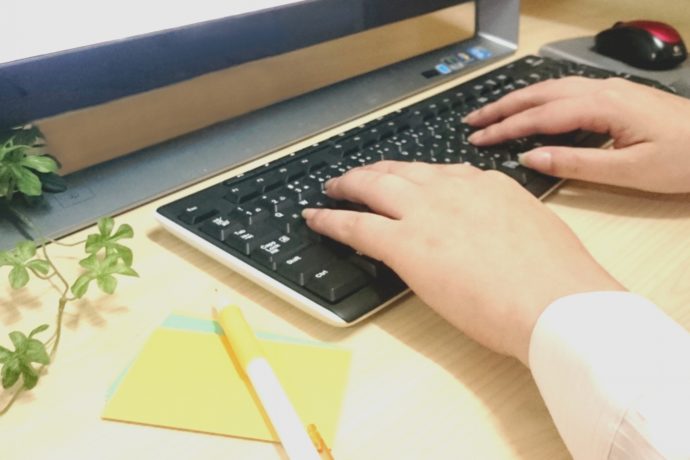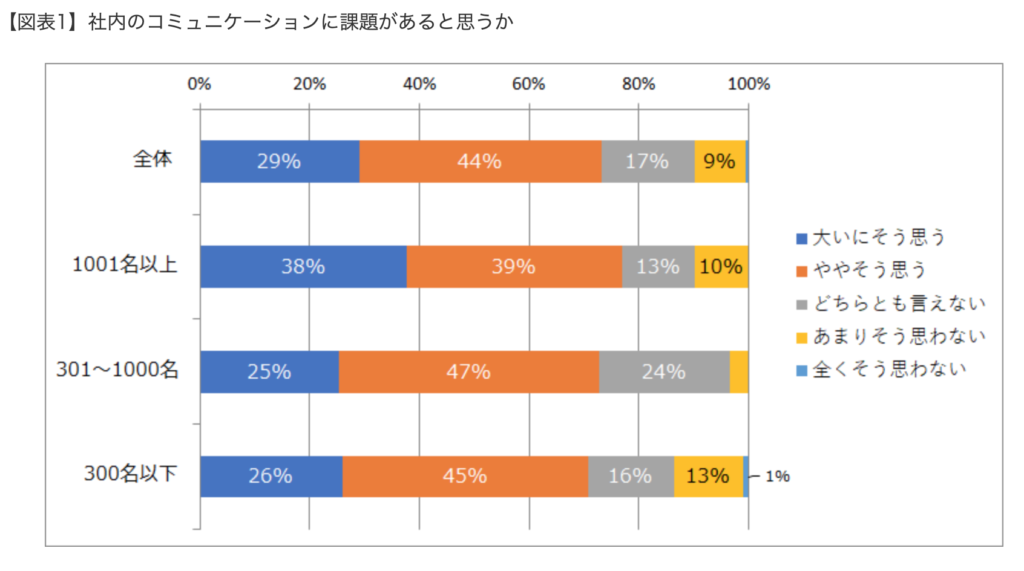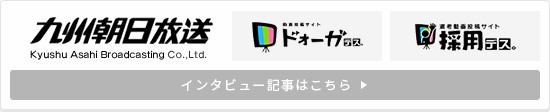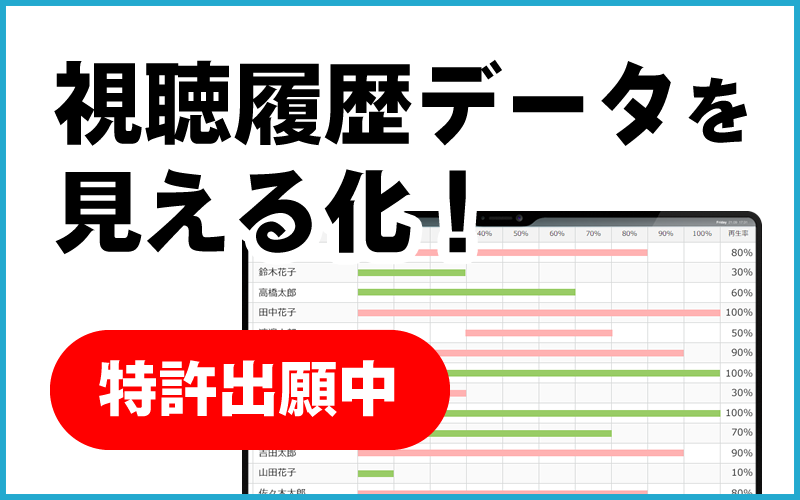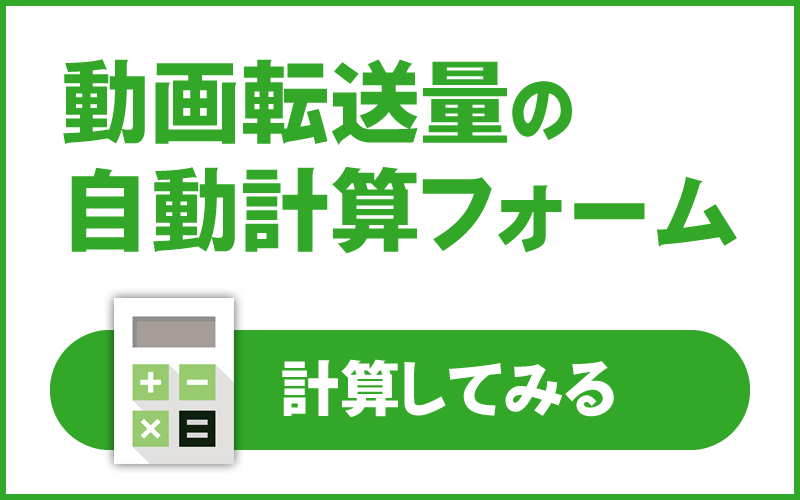企業が動画を使った企画を進めるにあたって、担当者は動画コンテンツの作成をどのように進めていくかについて考えなくてはなりません。
企画の目的や会社の方針によって状況は異なりますが、動画コンテンツを社内で内製化するか外注するかの判断はとても悩ましいところです。
内製化した場合には、低予算でコンテンツを作成できますが、クオリティーが担保できないなどの問題を感じることがあるかもしれません。外注した場合にはクオリティーを担保できたとしても、思った以上に費用が掛かってしまう場合もあります。
今回は、動画コンテンツ作成のフローを把握した上で、社内のリソースを割いて内製すべきか、外部の映像制作会社に外注するかの判断について押さえておくべきポイントを確認していきましょう。
動画コンテンツ作成のフローとは
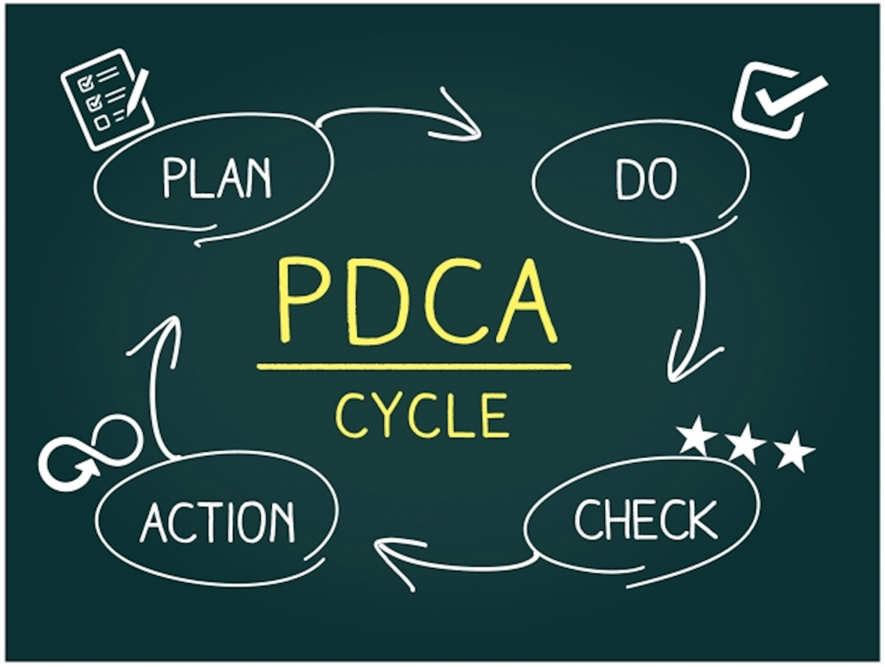
まずは動画コンテンツを作成するフローについて見ていきましょう。
内製でも外注でも動画コンテンツ作成における基本的なワークフローに大きな違いはありません。各フローについて詳しく見ていきましょう。
1. 方針の決定
動画作成を進めるに当たって企画立案前に動画コンテンツの方針を決定して、明確にしておくことは非常に重要です。
動画の場合、デザインやWEB製作などと比較して、作業が始まった後に方針を変更するのはとても難しく、制作スケジュールに大きな影響を及ぼしてしまうことがあります。
そのため、企画関係者で念入りに打ち合わせをし、動画を使う目的やその内容やターゲット、予算や納期などについて足並みをそろえておきましょう。
「動画企画のテーマ」や「動画を通して伝えたい事」など、具体的なイメージが決まっている場合は、できるだけ方針の詳細が固まるまで打ち合わせを重ねることが重要です。
2. 企画を固める
制作の方針が決まったら、その内容に基づいて企画を固めていきます。
企画書はメンバーがイメージしやすいよう、簡単なラフ画を添付するのが一般的です。
企画書の承認が得られた後、スケジュールやロケーション、予算などを考慮して、各スタッフの配置を決定します。
3. シナリオ・コンテ作成
企画が固まったらシナリオ・コンテを作成します。
シナリオは関係者するメンバーからフィードバックを得て、その内容を元にブラッシュアップします。これの作業が何度か繰り返されます。
最終的には「台本」として、各スタッフでその内容をきちんと共有します。
その後、ロケーションの下見やモデルの手配、小道具などの準備を行います。
4. 撮影
前行程で仕上げた「台本」を元に撮影をスタートします。
カメラや照明などの機材セッティングが完了したら、まずはテスト撮影を実施します。
テスト撮影で構図や音声などのチェックをし、問題がなければ、本番の撮影をスタートします。
5. 編集
撮影した映像や音声の素材をまとめて1つの動画に仕上げる編集作業に進みます。
必要な内容やカットが含まれているか大枠を確認することが重要ですので、仮のナレーションやBGMなどを挿入し、全体的な流れを見ながら仮編集を行います。
全てのシーンの確認が済んだら、本編集に入ります。
6. MA
本編集が完了したらMAに入ります。
MAとは「Multi Audio」の略称で、音の調整や収録作業を行う重要な工程です。
MAの作業の内容次第によっては、それまで作成した動画が一層引き立つか、まったく魅力のない作品になってしまうか、決定的な違いが生じてしまう可能性があります。
7. 試写・修正
本編集が完了したら、複数人による試写を実施します。
フィードバックの内容に応じて修正作業を行います。この段階ではよほどのことがない限り、映像を撮影し直すレベルの修正は実施しません。
あくまで、映像に入れるキャプションなどの微調整にとどめた作業が中心となります。
8. 納品
映像が完成したら、必要なファイル形式にエンコードし納品となります。
動画コンテンツを内製する際のポイント

社内のスタッフを中心として動画コンテンツを内製する場合のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
メリット
1. 最低限の予算設定が可能
一般的に映像制作に外注するとなると、尺の短い単純な内容であっても数万円〜費用がかかります。
アニメーションが入った製品紹介動画であれば十万円以上するものが相場で、手の込んだ内容であれば百万円以上する内容もザラです。
内製することでこれらのコストを社内リソースで賄い削減することが可能です。
2. 柔軟な対応が出来る
社内で制作する場合は、外注先とのスケジュール調整の必要はありません。
社内メンバーの空き時間を使って作業を進めることもでき、臨機応変にテーマやコンテンツを編集することが可能です。
また、社内リソースが許す限り動画の製作本数に制限はなく、欲しいと思った本数用意することが可能です。
全ての作業が社内で完結するため、機密情報の受け渡しの場合なども機密保持契約等を結ぶ必要がなく、契約書や煩雑な手続きによる影響を考慮する必要がないこともメリットと言えます。
3. メンバー間のコミュニケーションがスームーズに進行する
自社ブランドや商品について精通している社内スタッフが作成に関わることが可能なので、打ち合わせ時間を短縮することが可能です。
また、これまでの人間関係の土台があるので、コミュニケーションが取りやすく、かつ対面で頻繁に打合せのセッティングが可能です。
デメリット
1. 専門ソフトや撮影機材の準備に手間がかかる
動画の撮影や編集に必要な環境を整えるための時間的コスト・金銭的コストがかかります。
また、用意した機材やソフトをスムーズに使いこなせるまでに時間を要します。
2. 社内メンバーのリソースを消費する
当然のことながら社内メンバーをアサインしてそのリソースを消費することになります。制作業務に押されて本来するはずの業務が圧迫されることも考慮しなくてはなりません。
3. 動画のクオリティーを担保できない
通常、社内スタッフによる動画制作の素人同士が集まって手探りで作業を行う可能性があり、製作時間が膨らむ可能性があります。また、かけた時間に見合うクオリティが担保できるという保証はなく、むしろ難しいと言えます。
動画コンテンツを外注する際のポイント

次に、社外の映像製作会社を使って動画コンテンツを外注する場合のメリットとデメリットについてまとめます。
メリット
1. プロによる高品質な作品が期待できる
一般的な映像制作会社であれば、撮影機材やソフトウェアといった設備も最新のものを揃えています。また、動画を専門としている業者ならではの高品質な完成が期待できます。
2. 社内メンバーは本来の業務に集中できる
外注により社内メンバーが動画制作に割く時間は、方針の指示や撮影への立ち会い、確認作業などの最小限の作業に抑えることが可能です。
社内メンバーは本業に専念しながら動画を完成させられるので、手間がかかりません。
3. 専門家ならではのアイディアや助言を受けることができる
動画制作会社はそれを専門としているため、これまでの動画制作で培ってきた豊富なノウハウをもとに、社内メンバーでは思いつかないような効果的な演出や撮影方法、インパクトのある編集などを提案してくれます。
また、動画コンテンツの流行や最新の情報もとに助言をもらうことが可能です。
デメリット
1. コミュニケーションに時間がかかる
製品・サービスの特長、競合他社製品との違い、業界動向など、社内メンバーであれば共有されている基本的な情報を、正確に理解してもらうには相当の時間と手間が発生します。
また、時間をかけた場合も外注先にきちんと理解してもらえる保証もなく、内製に比べてコミュニケーションが大変です。
2. 想像以上に製作コストが膨らむ可能性がある
外部の専門家をアサインし撮影、編集を行うため、社内リソースでまかなえる内製のケースに比べて製作コストが高くなることは避けられないでしょう。
ユーザー投稿型サイトで動画コンテンツを集めよう
上記では動画コンテンツを準備する手段として、内製するか外注するかについてご説明いたしました。
その他の手段として、動画のユーザー投稿型サイト(CGM:Consumer Generated Media)を運用することで、動画コンテンツをユーザーから集めることができます。
ユーザー投稿型サイトを運用した企画の例としては、テレビ番組の「ネタ」となるようなスクープ映像を一般ユーザーから募集したり、就職採用試験の一環として志望者の自己PR動画を募集したり、お笑いコンテストのオーディション用の動画をテレビ番組視聴者から募集したりなど、過去にDOUPA!ブログでもご紹介いたしました。
参考:企業による動画投稿サイトの活用例と運用のポイントとは?
https://doupa.jp/info/866/
ユーザー投稿型サイトを運用する際のポイントとして次の4つを押さえておきましょう。
- ユーザー側が誰でも簡単にストレスなく動画を投稿できる仕組みがあること
- 投稿された動画やユーザー情報のセキュリティが担保できること
- 投稿された動画やユーザー情報をわかりやすく管理できること
- 企画の内容に応じて柔軟にカスタマイズできる環境
弊社が提供しているDOUPA!ポータルの「動画投稿プラン」は、動画投稿サイトの運用に必要な基本機能が最初からすべて揃っており、各企業様のニーズを汲んだ柔軟なカスタマイズ対応が可能です。
ユーザー投稿型サイトを運用する場合は、動画コンテンツを用意する必要は無くなりますが、企画を成立させるためのシステム選定や運用が重要となります。
内製と外注をうまく使い分けよう
社内で動画を制作するにも外注するにも、それぞれのメリットとデメリットがあります。
動画のクオリティーよりも制作費の削減が重要である場合、動画制作に社内メンバーが割くリソースが確保できる場合、社内に動画制作に精通した人がいて機材やソフトがすでに調達できている場合などは、内製がおすすめと言えます。
一方、予算を投じてでもクオリティーの高い動画が欲しい場合や、社員のリソースを確保できず制作作業との並行が難しい場合、社内に動画制作のノウハウを持つ人材がいない場合などは外注がおすすめです。
また、定常的な制作ニーズがあるかどうか、予算や納期、そして動画の目的によって内製か外注するかうまく使い分けてみることも重要でしょう。