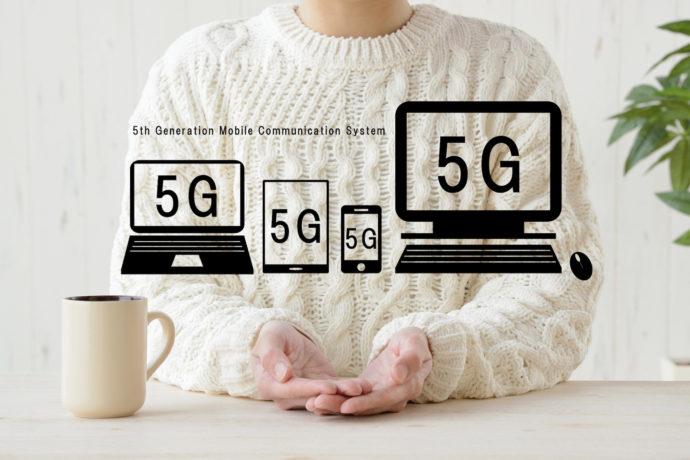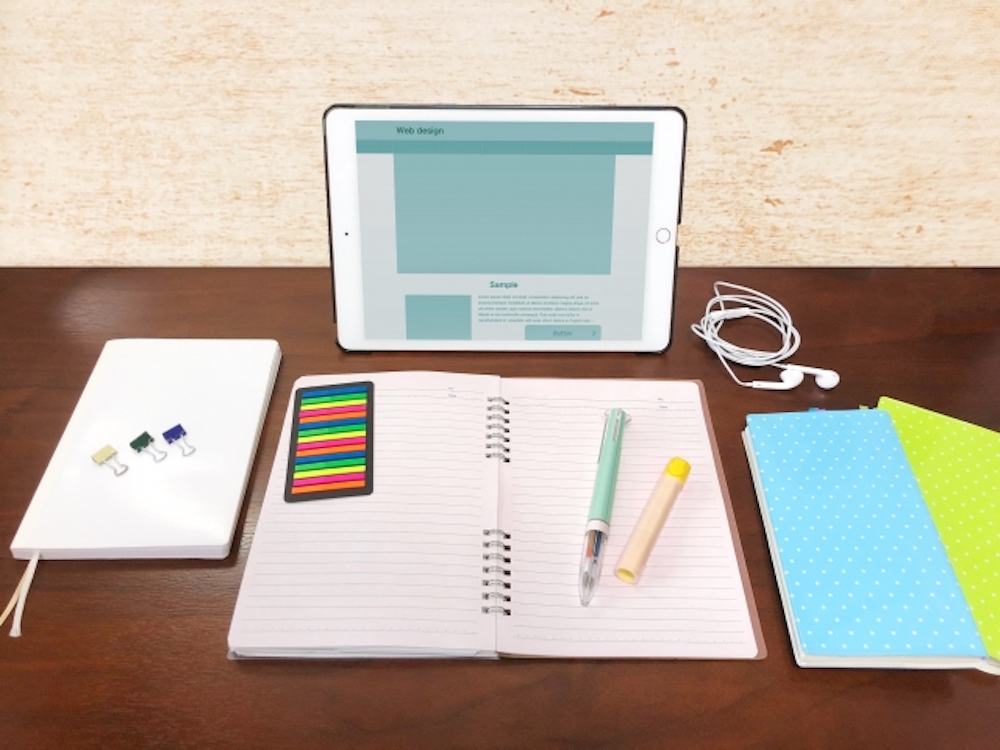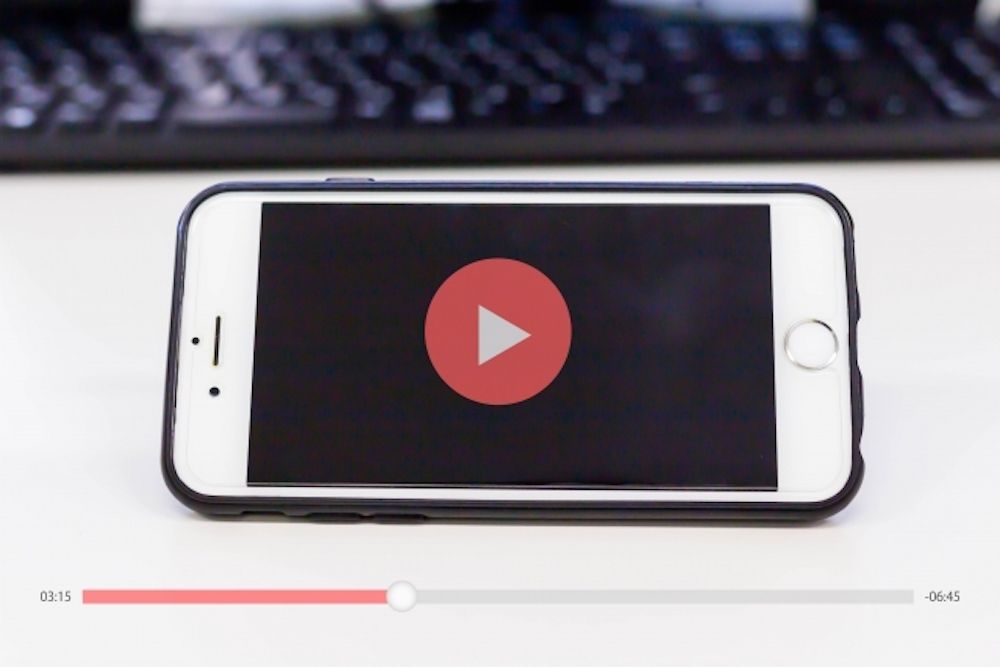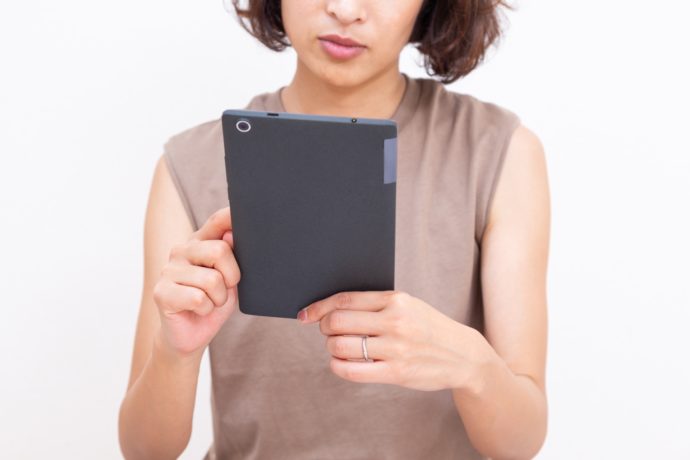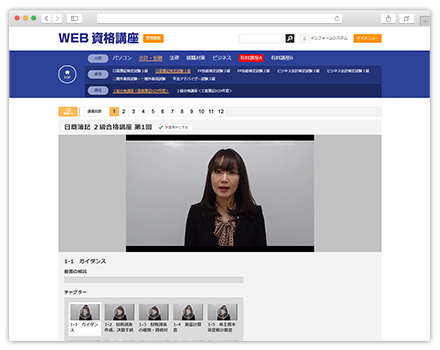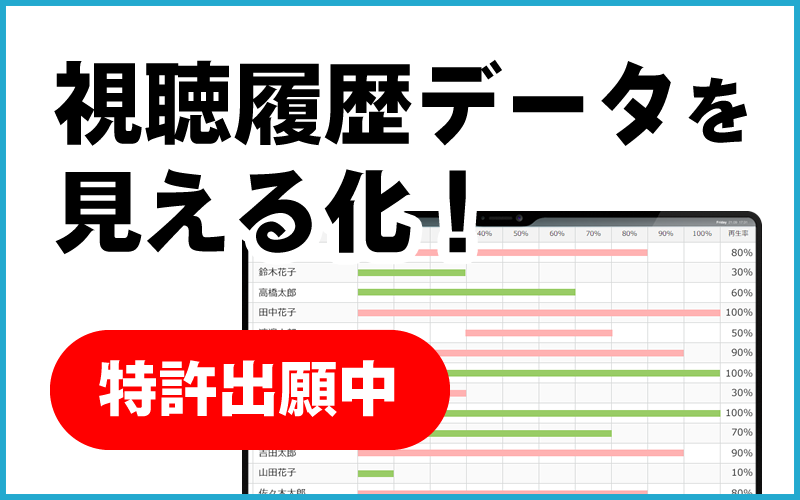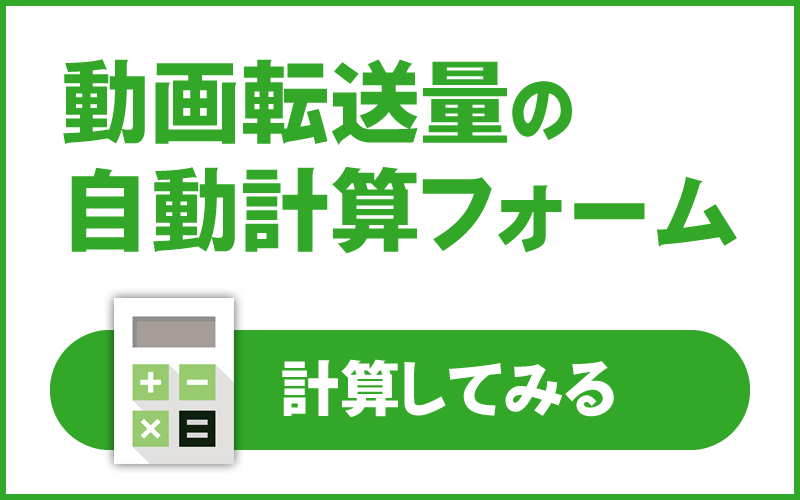動画配信サービスであるYouTube以外に、Facebook、Instagram、TwitterといったSNSを活用して動画コンテンツを配信する企業や個人が増えてきました。
一方でスポーツやエンタメ、eラーニング、資格講座、社内人材向け研修などの動画コンテンツを販売するために、動画販売システムの構築を行う企業も増えてきています。
今回は企業が動画販売を行うために知っておきたい、動画販売システムの構築方法についてご紹介いたします。
動画販売システムの構築方法について
企業がネットで動画を販売するためのシステム構築について、どのような方法があるのか見ていきましょう。
大きく分けてスクラッチでインフラを構築して動画配信を行う方法と、法人向け動画配信システムを利用する方法の2種類があります。
スクラッチ開発で動画販売システムを構築

スクラッチ開発とはシステムをゼロから作り上げることで、エンジニアや動画配信に必要なサーバなどを用意し、インフラを構築して動画を配信する方法です。
自社で人材やインフラの確保が難しい場合には、外注して開発を依頼する必要があります。
動画販売システムでは、企業が販売するコンテンツ内容や戦略・ターゲットなど様々な要素を考慮する必要があるため、パッケージを利用するよりも自由度の高いスクラッチ開発を導入した方が良いケースも少なくありません。
ただし、すべてゼロから開発できるという反面、開発期間が長くなりコストも高くなること、開発後のシステムメンテナンスや想定外のトラブルなどが発生する可能性も考慮しておく必要があります。
動画販売システムをスクラッチで構築する方法
動画販売システムをスクラッチ開発する場合、ウェブサイトやアプリケーションの開発と同様に、まずは販売する動画コンテンツの強み・特徴などを考慮した上で要件定義を行っていきます。
実際のフローを見ていきましょう。
1. 要件定義
スクラッチ開発の場合、ゼロからシステムを構築していくためパッケージを利用したシステム構築よりも手間やコストがかかります。
そのため、開発を無駄なくスムーズに進めるために、「どのような販売方法を行いたいのか」「どのような機能が必要なのか」といったことを要件定義で具体化し、抜け漏れをできるだけ無くしておくことが重要です。
2. 方式設計
方式設計では、データベース・ソフトウェアの構造設計、統合テストの要件策定を行い、販売システムの利用者がどのようにシステムを触るのかなども決定していきます。
ただし、詳細については詰めず、あくまでシステム全体の構成や構造といった骨組みを固めていきます。
3. 詳細設計
詳細設計では、方式設計で決定したデータベースやソフトウェアインターフェースなどのシステム要件を詳細部分まで設計していきます。
また、詳細設計の過程で方式設計に間違いや漏れがあった場合には、方式設計の内容を見直します。
4. システム実装・開発
実装・開発段階では、詳細設計で決定した内容を元にプログラミング・デザイン・コーディングを行います。
5. 単体・結合・運用のテスト
実際に実装したシステムの確認・テストを行います。
システムがそれぞれの機能要件を満たすことができていなければ修正作業を行い、システムを仕上げていきます。
法人向け動画配信システムを利用して動画販売を行う
スクラッチでゼロから動画販売システムを構築するのではなく、法人向け動画配信システムを利用して動画販売を行う方法です。
動画配信プラットフォーム・動画配信CMSなどとも呼ばれており、オンデマンド配信やLIVE配信に利用出来るサービスがあります。
スクラッチ開発とは異なり動画販売に必要な機能が既に含まれたパッケージのため、そのまますぐに利用できるメリットがあり、一部のみカスタマイズするといった相談も可能です。
開発において費用の削減が見込めることや、リリースまでの期間も短いため、スモールスタートを行いたい企業にとってピッタリです。
法人向け動画配信システムを利用して動画販売を行う方法にも2種類あり、SaaS(Software as a Service)としてレンタル利用する方法と、パッケージを買い取って販売を行う方法が挙げられます。
SaaSの法人向け動画配信システムを利用して動画販売を行う
月額制のSaaS(パッケージレンタル)を利用すれば、費用を抑えて短期間で動画販売システムの構築を行うことができます。
また、サーバーもパッケージを提供している会社が用意しているものを使用するため、すぐにサービスを始めることができ、簡単なデザイン変更も行えます。
法人向け動画配信システムを買取して動画販売を行う
法人向け動画配信システムの中にはパッケージ買取が可能な場合もあり、自社の商品やサービスに合わせた機能カスタマイズなどが可能です。
自社独自の機能を追加したい場合やデザインをフルカスタマイズしたい場合などにおすすめです。
ただし、レンタルとは異なりサーバー構築やカスタマイズの考慮など、リリースまでに時間が必要になります。
具体的な開発フローは自社でゼロから構築するスクラッチと同様ですが、必要な機能を自社で実装可能かどうかなどを事前に確認しておきましょう。
動画販売システムを構築する際の注意点

動画販売システムを構築する際には「見積もりと工数の確認」や「実績がある会社かどうか」、「自社に必要な機能のカスタマイズが可能かどうか」を確認しましょう。
1. 見積もりと工数の確認
スクラッチ開発やパッケージ買取でのカスタマイズを検討する場合には、開発前の見積もりのタイミングで「提案した機能の実装にどれくらいの費用や工数がかかるのか」「納品後に不具合が発生した場合の対応はどうなるのか」などを確認しておくことが大切です。
開発スケジュールや費用の見積もりが甘ければ「プロジェクトの進行が遅れてしまう」、「想定外の出費が発生し予算オーバーしてしまう」などのリスクが考えられます。
2. 実績の有無
スクラッチ開発でもパッケージを利用する場合でも、動画配信に関する開発実績はどの程度あるか、どれくらいの企業が導入しているのかなどを事前に確認しておきましょう。
例えば、eラーニングの動画コンテンツを販売したい場合は、eラーニングを販売するためのシステムを構築している企業の実績を確認してみましょう。
自社の動画販売システムを構築する際の参考材料にすることができますし、信頼して任せることもできます。
守秘義務の関係でサイトには実績として挙げていない場合もありますので、興味・関心があれば一度問い合わせてみましょう。
3. 機能のカスタマイズ
スクラッチ・パッケージ共に、自社が管理する動画販売システムに必要な機能を実装可能かどうか必ず確認しましょう。
自社でスクラッチ開発する場合は社内の担当者や外注先に確認を取り、パッケージを元にカスタマイズを依頼する場合は依頼先の企業に導入可能かどうか、機能の調整や追加を途中で行うことができるかなどを確認しましょう。
自社にとって最適な方法で動画販売システムを構築しよう
5Gの登場も追い風となり、動画配信は今後ますます増加していくことが見込まれます。
動画販売をお考えの場合、上記で挙げた3つのパターンの中から最適な構築方法を選択することが重要です。
それぞれのメリット・デメリットを検討した上で、自社に合った方法で動画販売システムを構築しましょう。