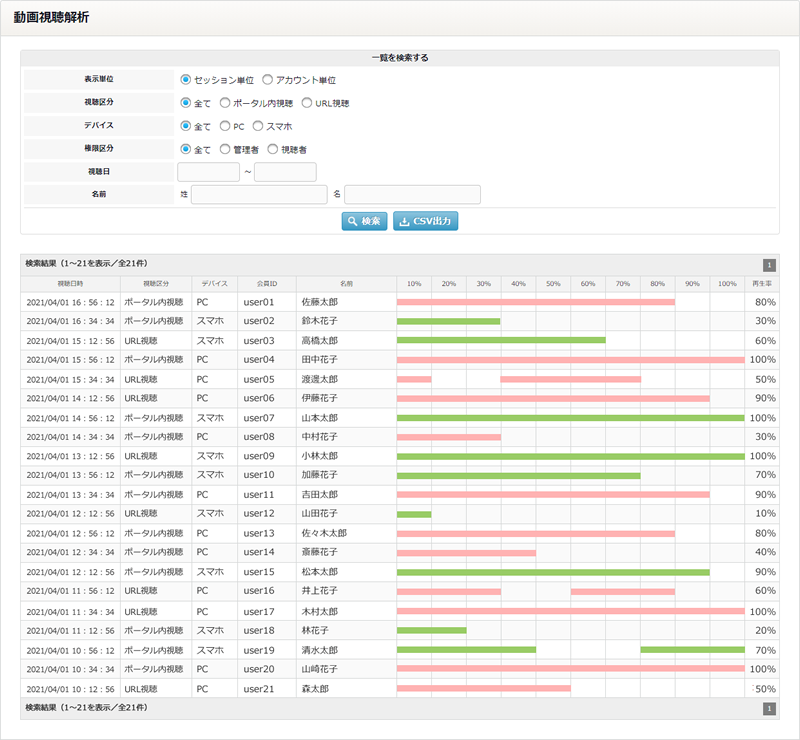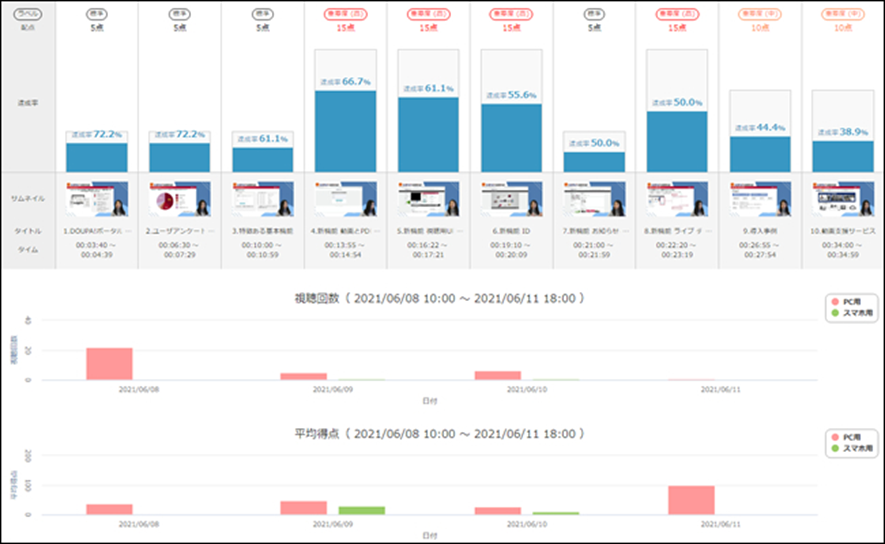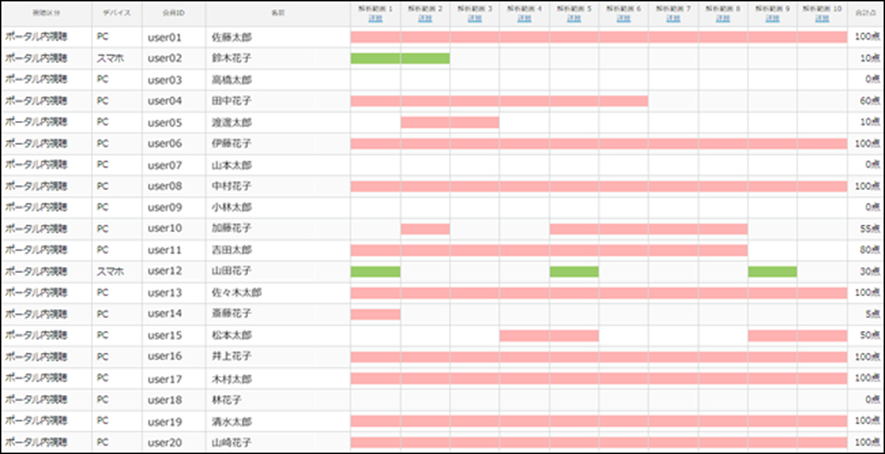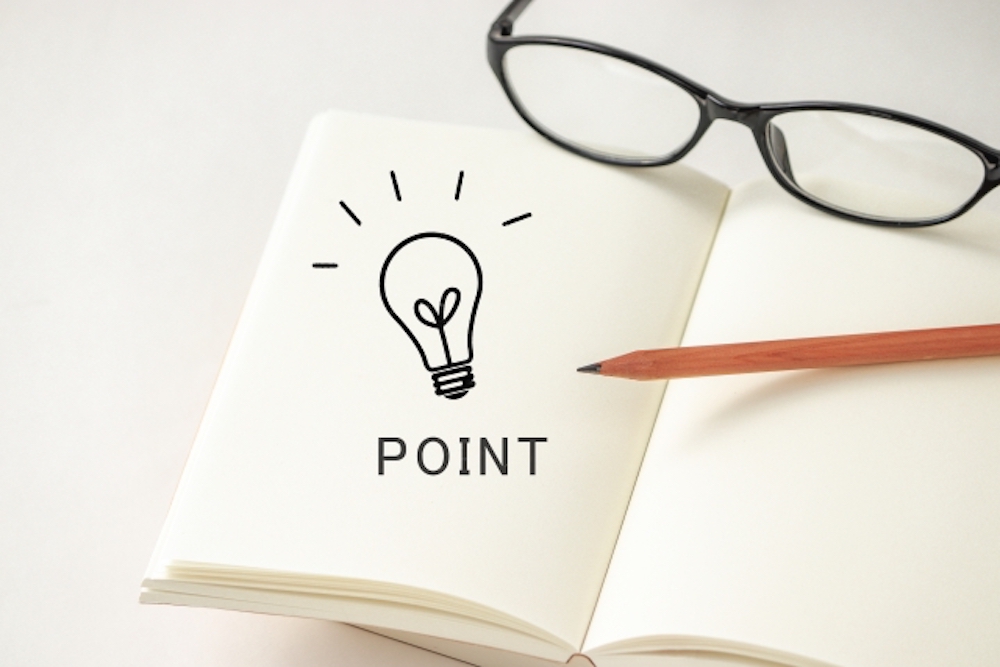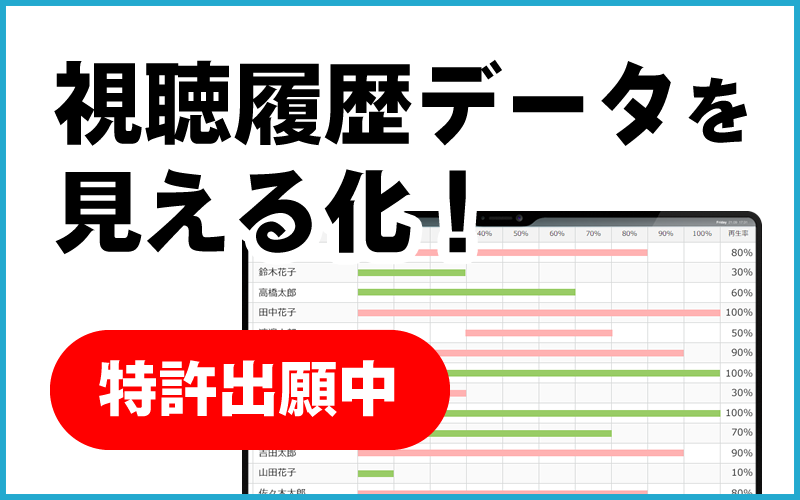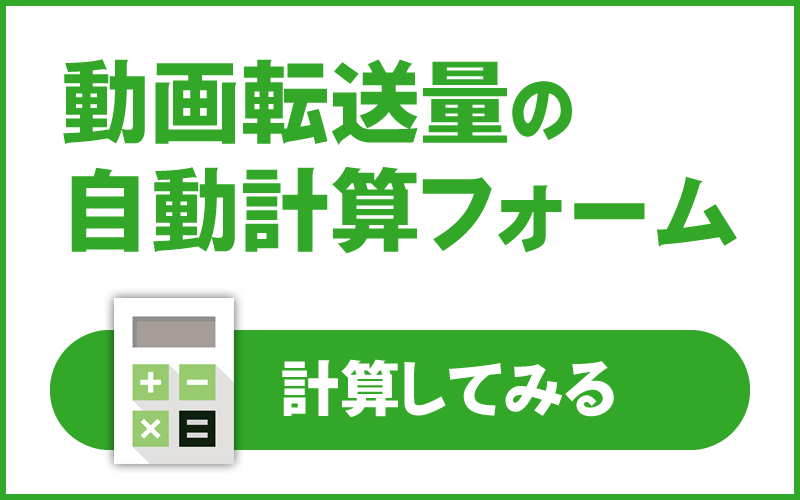動画が視聴できるデバイスの高性能化やインターネット環境の強化が年々進み、さらにモバイル通信キャリアの5Gエリアも拡大を続けています。それに伴い、より高画質な動画が視聴者に好まれるため、動画サイズ(画質)も大きくなる傾向にあります。
インターネットで動画配信をする場合は、動画サイズは動画配信そのものに大きな影響を与えるので、きちんと概念を理解し、最適なものを選択するようにしましょう。
特に企業内や組織内の動画配信システムでは、画質にこだわり過ぎると社内ネットワークのトラフィックに負荷をかけてしまう恐れや、外部の動画配信サービスを利用する場合には転送量や容量で課金されるのが基本になりますので注意が必要です。
まずは動画サイズ(画質)の基礎について整理してみましょう。
動画サイズの基本
まず動画サイズの基本を理解するためには「ピクセル」「画面解像度」「アスペクト比」の各ワードについてポイントを押さえましょう。
ピクセル
ピクセル(px)とは、デジタル画像の最小単位のことを指します。
デジタルの動画や画像を限界まで拡大して引き延ばすと、小さな点の集合で構成されていることが分かります。この各々の点が1ピクセルです。
画面解像度
動画における画面解像度とは、動画の縦横のピクセル数や画素数を表す言葉です。
画面解像度が高ければたくさんの画素で表現することになり、鮮明で詳細な高画質な動画ということになります。
例えばフルHDの画面解像度は1920×1080や1080Pと表現されます。
これは横1920個×縦1080個のピクセルで描写された動画ということを表しています。
アスペクト比
アスペクト比は動画の縦横比のことを指し、ワイド(16:9)の比率が標準となります。
※2000年代前半までの多くの映像のアスペクト比は4:3が主流でしたが、現在は4KやフルHDなどに代表される16:9が主流となりました。
テレビやモニター、撮影機材なども16:9の映像が最適に視聴できる仕様となっています。
スマートフォンのアプリでは縦長の動画も見られるようになってきており、必ずしも横長だけのアスペクト比とは限りません。
一般的な動画サイズ
以下では、よく使われる一般的な動画サイズの名称と画面解像度を確認していきましょう。
4K
2160p=画素数:4096×2160 or 3840×2160/アスペクト比 256:135 or 16:9
最近では4K対応のテレビが標準で、8Kテレビなども販売されています。
NetfilixやHuluなどの有料動画配信サービスも4K配信に対応しています。
フルHD
1080p=画素数:1980×1080/アスペクト比 16:9
HD
720p=画素数:1280×720/アスペクト比 16:9
SD
480p=画素数:854×480/アスペクト比 16:9
※従来は、画素数:720×480/アスペクト比 4:3で地上波アナログテレビ放送時代で使用された解像度に近い動画サイズとなりますが、現在ではほぼ使われません。
※インターネット配信で、特に企業内や組織内では基準となる動画サイズになります。
(参考)YouTubeが推奨するアップロード時の動画サイズ
代表的な動画サイズとして、無料動画配信サービスであるYouTubeが推奨する動画サイズを頭に入れておきましょう。よく使われる動画サイズのトレンドを把握することができます。
※HDや4Kなどの規格名より、YouTubeで目にする480Pや1080Pの方がサイズ感がつかめやすく普段使いにはこちらをお勧めします。
- 2160p:3840×2160(4K)
- 1440p:2560×1440(2K)
- 1080p:1920×1080(フルHD)
- 720p:1280×720(HD)
- 480p:854×480(SD)
YouTubeで5分間の動画をアップロードする場合、解像度やビットレートによってファイルサイズが変わります。以下に、解像度別のファイルサイズの目安を示します。
- 4K:約500MB以上
- フルHD:約200MB
- HD:約100MB
- SD:約50MB
引用:YouTubeヘルプ
YouTubeの動画プレーヤーは、アスペクト比が16:9に設定されています。
アスペクト比4:3の動画をアップロードすると、動画プレイヤーのスクリーン内に、上下もしくは左右に黒帯が表示されます。この上下・左右に黒帯が表示される理由は、YouTubeが自動で動画スクリーンに合わせてサイズを調整しているためです。
動画の企画や配信に携わる際は、どれぐらいの画面解像度が最適なのかをしっかり考えてから行うことで失敗が少なくなりますので意識してみましょう。
広告、プロモーションの動画配信と、企業内や組織内での動画配信では用途が大きく異なり、動画サイズの設定も違ってきます。
企業内や組織内で考えてみますと、資料ベースの研修動画は480Pで十分ですが、人が操作する技術指導動画であれば720Pはほしいところです。
転送量や容量との兼ね合いもありますので、下記リンク「転送量の自動計算フォームはこちら」で想定される視聴人数、視聴時間、動画サイズ(画質)を入力選択して計算してみてください。